
メールで上手になる方法
好むと好まざるにかかわらず、電子メールは私たちの多くのオンラインコミュニケーションの基礎となっています。電子メールは、時間の経過とともに現れたり消えたりするサービスから独立した信頼できるチャネルを提供するからです。では、電子メールを最大限に活用するにはどうすればよいでしょうか?

メールから必要なものを取得する
ソーシャル メディアでの会話、テキスト メッセージ、さらには電話とは異なり、電子メールには、他のオンライン コミュニケーション メディアでは伝えにくいレベルの永続性と、多くの場合、真剣な態度が含まれています。
そのため、実際に入力を始める前に、メールに何を求めるかを考えてください。それが単なる転送されたジョークである場合は、おそらく送信する価値はありませんが、二次当事者から情報やアクションを取得しようとしている場合は、できるだけ早くそれをできるだけ明確にします。保存される電子メールは、特に初めて誰かに連絡する場合、すぐに忘れられてしまうものです。
(画像クレジット: 写真提供: Terry Presley/Flickr/CC BY-SA 2.0)
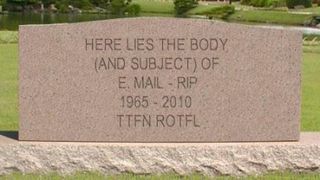
件名
メールの件名は宣伝文句だと考えてください。ユーザーの注意を引く時間があまりないため、広告は通常、短く簡潔です。あなたが送信するどのメールにもまったく同じことが当てはまります。すべての電子メールがすべて読まれるわけではありませんが、電子メールを使用している人なら誰でも、少なくとも定期的に受信トレイの件名に目を通すでしょう。
件名は簡潔にすることが大切であり、これはメール全般に適用する価値のある原則です。主題を短くパンチの効いたものにすると目立ちますが、すべてを大文字にしたり、不必要な句読点をたくさん入れたり、転送されたときに当惑したりイライラさせたりする可能性のあるものをすべて入れたいという衝動を抑えてください。
(画像クレジット: カンボジア 4kids.org/Flickr/CC BY-SA 2.0 による写真)

いつ送信するか
電子メールを送信する「最適な」時間については、絶対的な厳密なルールはありません。それは、内容と、送信者と受信者の間の関係の両方に依存するためです。
職場環境では、ほとんどの人が勤務日の比較的早い時間に受信箱をチェックするため、小さくて簡単に実行できるアイテムに対処するのが最適かもしれませんが、それらが潜在的に数百ものアイテムを調べていくという事実と比較検討する必要があります。他のメールも同時に送信できます。
長くて内容の濃いテキストを送信する場合、人々が仕事でリラックスする午後遅くに送信される可能性が高いことを示唆する証拠があります。ただし、ビジネスメールの受信率が高い週末には同じことが当てはまりません。スマートフォンの常時接続の世界でも顕著に減少する傾向にあります。
(画像クレジット: 写真提供: Alan Cleaver/Flickr/CC BY-SA 2.0)
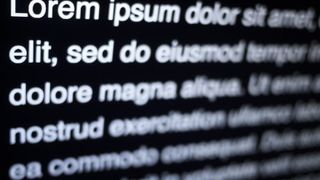
メールに何を記載するか
おめでとう!件名は機能し、受信者はあなたの電子メール自体を見ています。ここでも、メールから望む内容を得るには、物事をシンプルかつ簡潔に保つことが最善の策です。
質問したりアクションを要求したりする場合は、それをメールの中心に置きます。受信者が単にメールを流し読みしたり、読んでいる間に気が散ってしまうリスクが常にあるためです。自分の主張をはっきりと述べると、多くの場合、受け手の側の行動につながりますが、大げさに言ってしまうと、すぐに相手を失ってしまいます。あなたのもののほかに、おそらく 100 件以上のメールが存在することを忘れないでください。
近年、ブロードバンド接続が著しく改善されましたが、それでも、電子メールで送信する添付ファイルの数を制限することをお勧めします。受信トレイの設定によっては、特定のサイズを超える添付ファイルを単に拒否するものもありますが、たとえその制限内に制限したとしても、受信者がどこからメールにアクセスするかを制御することはできません。
自宅やオフィスの高速接続を使用している可能性もありますが、同様に不安定なモバイル接続を使用している可能性もあり、データ KB ごとに料金が発生し、ネットワークのユーザーが飽和しているためにデータの供給のみが行われます。疑わしい場合は、大きな添付ファイルにはDropboxなどのオンライン ストレージ サービスを使用して、受信者が必要なときに必要なときに大きなファイルにアクセスできるようにします。彼らはそのジェスチャーに感謝し、結果としてメールの印象が良くなるでしょう。
(画像クレジット: 写真提供: Blake Burkhart/Flickr/CC BY-SA 2.0)

送信フィールド
電子メールの To: フィールドが何のためにあるのかは誰もが理解しています。これは、物理的な封筒の外側に付けていたアドレスと同じ機能を果たすためです。しかし、それを超えると、混乱と間違いが蔓延します。
まず、CC があります。これは「Carbon Copy」の略です。これは二次電子メール受信者を対象としており、ディスカッションの性質について追加の相手に警告するという基本的な考え方を持っています。ここでの典型的な例は、同僚と仕事のプロジェクトについて話し合っているときに、そのプロジェクトが特定の方法で扱われていることをマネージャーに警告したい場合です。デジタル ペーパーの痕跡と認識が作成されるためです。
問題は、どのメール クライアントでも、「To:」または「CC:」フィールドに複数の電子メール アドレスを入力できるということです。厳密に言えば、To: フィールドは、メールの件名に関して直接のアクションを受け取りたい相手に使用する必要がありますが、常にそのように扱われるわけではありません。
(画像クレジット: RaHuL Rodriguez/Flickr/CC BY-SA 2.0 による写真)

リコールを押さないでください!
一部の電子メール システムは「取り消し」機能を提供しますが、これは、同じクライアントおよびサーバー環境 (通常は Microsoft Exchange と Outlook) を持つ電子メール チェーンの両端に依存するため、ほとんどの場合、本質的に冗長です。
誰かが別のクライアント経由で電子メールにアクセスした瞬間、元の電子メールの取り消しを要求するメッセージが送信されるだけで、取り消しが行われます。これが実際に行うことは、あなたが何らかの間違いを犯したことを明るく輝く文字で指摘することだけです。間違って送信されたものについては、機械で生成された謝罪メッセージよりもすぐに謝罪メッセージを送信する方が、おそらくより良いエチケットです。
不用意なメールが気になる場合に役立つ 1 つの方法は、選択したメール クライアントで、「送信」ボタンを押した後、特定のメールの送信を 1 ~ 2 分間遅らせるルールを設定することです。そうすることで、メッセージを検討し、もう一度読んで、送信トレイから送信される前にキャンセルするための少しの時間が生まれます。
ただし、唯一の例外は Gmail で、Web インターフェイスに新しい「送信取り消し」機能が正式に導入されました。

いつ、どのように返信するか
ただし、CC には二次的な、より大きな問題があり、それは大規模なグループに送信したり、返信を期待したりする場合に発生します。[To:] フィールドまたは [CC:] フィールドに電子メール アドレスを入力すると、その電子メール アドレスが電子メールを受信するすべての当事者に公開されるだけでなく、「全員に返信」を使用するすべての返信の直接行にそのアドレスが追加されます。
CC: フィールドで 2 人の間で長い電子メールの会話が勃発し、1 人が「全員に返信」をしつこく使用すると、すぐに自分とは関係のない数十通の電子メールが大量に送信され、迷惑な受信者が増え続けることになります。これは単純な電子メール エチケットに対する最も一般的な違反ですが、ありがたいことに解決策は非常に簡単です。
では、どのような場合に全員に返信機能を使用すればよいのでしょうか? 自分の返信が To: および CC: フィールド内の全員に表示されたり、アクションを実行される必要があると確信している場合。そうでない場合は、元の送信者にのみ単純な返信を使用するか、返信に対する入力や認識が必要ない送信者を編集して削除します。
(画像クレジット: AJCI/Flickr/CC BY-SA 2.0 による写真)

BCCの力
BCC: (ブラインド カーボン コピーの場合) フィールドを使用すると、To: フィールドまたは CC: フィールドに追加するのと同じ方法で、特定の電子メールにループするアドレスを追加できます。ただし、重要な違いがあります。BCC: では、BCC: フィールド内のリストは送信者以外には完全に見えないままになっているためです。
To: フィールドの受信者にも BCC: 受信者は表示されません。これにより、To: フィールドに自分の電子メール アドレスを入力し、BCC: フィールドに他のすべての受信者を入力するだけで、フォローアップ メールを望まない、または必要としない可能性のあるユーザーを阻止する、非常にシンプルな通信ループが可能になります。
すべての受信者はあなたの電子メールを受け取るだけで済み、あなたは最初に確認コピーを受け取り、それがインターネットの曲がりくねった廊下で紛失していないことを確認し、同時に他の人の電子メール アドレスを公開することはありません。
(画像クレジット: 写真提供: Stuart Richards/Flickr/CC BY-SA 2.0)